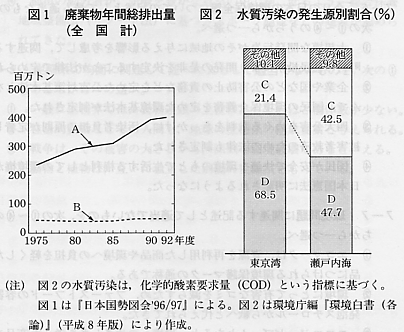
GSYZ07
7 公害・環境問題
7-1 日本の公害問題に関連する記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
日本では,企業活動に起因する産業公害だけでなく,国民の日常生活から生じる生活公害も問題になっている。
②
それ自体は無害・安全な物質であっても,他の物質と複合して危険なものに変化し,環境を汚染する場合もある。
③
騒音や悪臭は,人間の生命に直接危害を与えないので,環境基本法では,「公害」から除外されている。
④ 公害は発生源で防止する方が,発生した後で取り除くよりも効果的に対処できる。
7-2 日本の産業廃棄物に関連する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
OA(オフィス・オートメーション)化が進展し,フロッピー・ディスクやCD等の記録媒体が普及したことにより,紙の消費は減少してきている。
②
条約によって海外での産業廃棄物処理が不可能になったこともあり,日本の産廃処理問題は深刻度を増している。
③
日本的経営方式の代表ともいえる「かんばん」方式は,大量の産業廃棄物を生み出すために見直しの声があがっている。
④
ハイテク企業は無公害だと考えられていたが,IC(集積回路〉製造工程で光化学スモッグを引き起こすことがわかった。
7-3 日本における家庭などから出る-般廃棄物についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
自治体が収集したゴミは,それぞれの行政区域内の処分場において処理しきれないことも多い。
②
家庭からのゴミは有害な物質を含まず,焼却されたり埋め立て等に用いられたりするため,これまで問題化したことはない。
③
大量消費は,資源の浪費の問題であるだけでなく廃棄物処理の問題でもあり,これらは消費者問題と呼ばれている。
④
ゴミ焼却施設の焼却灰から検出されるカドミウムは,米軍がベトナム戦争時に使用した枯薬剤にも含まれていた発ガン性のある猛葦物質である。
7-4 次に二つの図をあげた。図1は産業廃棄物と一般廃棄物(ただし「し尿廃棄物」を除く)の年次変化を示したグラフである。図2は,水質汚染源としての産業排水と生活排水の割合を,1989年の東京湾(人口密集
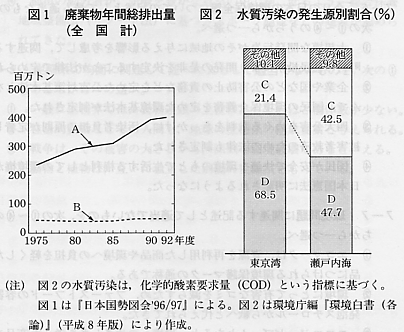
① A 産業廃棄物 B 一般廃棄物 C 産業排水 D 生活排水
② A 産業廃棄物 B 一般廃棄物 C 生活排水 D 産業排水
③ A 一般廃棄物 B 産業廃棄物 C 産業排水 D 生活排水
④ A 一般廃棄物 B 産業廃棄物 C 生活排水 D 産業排水
7-5 日本における公害防止策に関連する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
工場からの排出物については規制が行われたが,自動車の排気ガスについては規制されていない。
②
排出される汚染物質の絶対量を規制する総量規制方式は,大気や水質の汚染防止に効果がなかったので,廃止された。
③
公害を防止したり汚染を除去したりするための費用は,汚染原因者の負担とする,という考え方が登場した。
④
公害対策は全国共通の基準で行われる必要があるから,地方自治体には独自に規制を行う権限は与えられていない。
7-6 今日の日本の環境保全策についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
大規模な開発行為がその地域に与える影響を考慮して,関連する市町村の住民投票により開発の是非を決定することが法律で定められた。
②
企業や国などの公害防止の責務などを定めた公害対策基本法とならんで,国民の環境保全義務を定めた環境基本法が制定された。
③
四大公害をめぐる裁判をきっかけに,汚染者負担の原則が定着し,被害者救済のための法律も制定された。
④
国民が安全で快適な環境のもとで生活する権利としての環境権が,日本国憲法に明記されるようになった。
7-7 環境問題に関連する記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
エコマークは,資源を再利用した商品や環境への負担を軽くした商品につけられる環境保護マークの通称である。
②
環境にとって有害なゴミを減らすため,ファーストフードの容器が,発泡スチロールから紙へと代えられてきた。
③
エコロジーがブームとなると,環境へのやさしさを考えた商品を製造販売するエコ・ビジネスが生まれた。
④
フロンは人体に付着すると有害であり,皮膚ガンを引き起こす原因となるため,代替フロンが開発された。
7-8 環境問題への取り組みとして適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
自然環境を破壊から守るために,広く寄付を募って森林や緑地を住民が買い取り,保存・管理するナショナルトラスト運動が,各地で広まってきた。
②
再生紙使用のトイレットペーパーなど,自然環境の保全に貢献する商品には,環境保護マーク(エコマーク)がつけられるようになってきた。
③
憲法に根拠づけられた新しい人権として,プライバシーの権利や知る権利と並んで,環境権が主張されてきた。
④
都市の勤労者が,余暇を豊かな自然の中で過ごせるよう,総合保養地域整備法(リゾート法)に基づきスポーツ施設などの建設が進められてきた。
7-9 生態系の均衡に関連して述べた又として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
一般に生物界では,食物連鎖の上位にあるものほど個体数が少ない。
②
社会的動物としての人間も,地球の生態系の構成要素と考えられる。
③
戦争は,その被害の大きさから,深刻な環境破壊であるといえる。
④
動物と植物は,互いに独立した別個の生態系をもっている。
7-10 地球的規模の環境問題の諸要因とされているものを図に示すと,次のようになる。この図のA~Cに当てはまる組合せとして正しいものを,次の①~⑥のうちから一つ選べ。
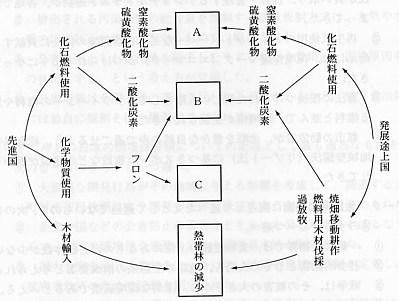
① A 酸性雨 B 地球の温暖化 C オゾン層の破壊
② A 酸性雨 B オゾン層の破壊 C 地球の温暖化
③ A 地球の温暖化 B 酸性雨 C オゾン層の破壊
④ A 地戌の温暖化 B オゾン層の破壊 C 酸性雨
⑤ A オゾン層の破壊 B 地球の温暖化 C 酸性雨
⑥ A オゾン層の破壊 B 酸性雨 C 地球の温暖化
7-11地球的規模の環境破壊の例として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
フロンガスが原因とみられるオゾン層の破壊が,低緯度地域を中心に進行している。
②
アフリカなどでは,過放牧,過度な耕地拡大などによって,砂漠化が進行している。
③
二酸化炭素などの濃度の増大によって平均気温が上がれば,地球の海水面が上昇するおそれがある。
④
ヨーロッパなどでは,硫黄酸化物や窒素酸化物が溶け込んだ酸性雨などによって,森林の樹木が枯死している。
7-12 化石燃料の大量使用による二酸化炭素の増加が地球温頓化の原因の一つと考えられており,排出量の削減に向けて様々な取り組みがなされている。排出量削減のための国際的取決めの記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
世界各国は,それぞれの国が二酸化炭素の排出量を同じ割合で削減することに合意している。
②
国連は,地域ごとに二酸化炭素の総排出量削減目標を設定したが,割り当てに関する加盟国間の合意はできていない。
③
二酸化炭素の排出量を減らすには,大量に排出している発展途上国が先進国に先立って削減に取り組まなければならないという合意ができている。
④
二酸化炭素の排出量を減らすには,産業構造の転換も必要になるので,先進国間でも削減割合を一律に設定するという合意はできていない。
7-13
酸性雨が主たる原因の一つとなって森林破壊が発生している地域として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
ドイツ南西部の「黒い森」
②
アマゾン川流域の熱帯雨林
③
北アメリカ五大潮周辺の森林
④
中国の内陸工業地帯周辺の森林
7-14 地球規模の公害防止のために役立つとは言えないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
地球環境保護のための国際条約が,あらゆる団によって遵守されるように,発展途上国に対する公害防止等の援助を増大させる。
②
国際分業関係の再配置を通じた国内産業構造の転換を進め,公害防止が技術的に困難な業種の自国内での割合を小さくする。
③
海外に新たに進出する企業が,本国の旧式の設備を移転するのではなく,省エネルギー型の最新設備を導入する。
④
太陽エネルギーのほか,バイオマスなどの再生可能なエネルギーの開発や実用化を進める。
7-15 環境問題に対する市民団体の国境を越えた取り組みの記述として、最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
日本の家庭に眠っている毛布を,戦火によって住居を失ったアフリカの難民に送るための活動が,ボランティア・グループによって広く行われてきた。
②
経済協力開発機構(OECD)は,工業諸国の訪問調査を通じて,各国の環境政策とその成果を評価した報告書を定期的に作成している。
③
東南アジア地域における公害の発生状況についての監視能力を高めるために,日本の反公害グループによる現地住民の訓練が行われてきた。
④
日本では市町村が公害防止の業務を直接に担当しているので,アジアの発展途上国に大都市の職員を派遣して,環境保全業務の指導を行っている。
7-16 途上国における工業化にともなう環境破壊に対する対策が不十分である理由を説明した文として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
多くの途上国では,自然は人間によって支配されるべきものとする伝統的な考え方が根強いから。
②
多くの途上国では、自然環境が破壊されても成長の速い熱帯林によっていずれ修復されるから。
③
多くの途上国では,外国資本による環境破壊については,規制の対象から除かれているから。
④
多くの途上国では,貧困や人口爆発等の問題があり,環境保全に取り組むだけの経済的余裕がないから。
7-17 先進国と途上国の環境をめぐる利害の対立に関連する記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
発展途上団での環境破壊には,「公害輸出」と呼ばれるように,先進国の企業によって引き起こされるものもある。
②
先進国による発展途上国への援助は,環境保全や公害防止をめざすものではなく,開発に目的を限定している。
③
発展途上国は,環境を守るための地球規模の政策が,自国の開発を制約するのではないかと懸念している。
④
環境保全と開発を調整するために,「持続可能な開発」という考え方が提唱されている。
7-18
「持続可能な開発」という考え方の趣旨を表す文として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①
現在の開発による環境破壊の損失は,将来の所得上昇によって補償される程度でなければならない。
②
現在の経済的欲求を満たすためには,将来の世代は一定の環境破壊を甘受すべきである。
③
将来の世代が豊かな社会を享受するために,開発は環境の保全と両立するものでなければならない。
④
将来の経済発展によって環境破壊はますます拡大すると予想されるから,新たな開発は中止されるべきである。