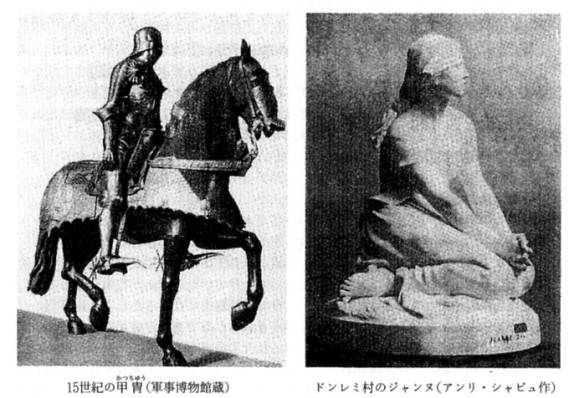
第5章 現代の諸課題と倫理
3.異文化理解と人類の福祉
5-3-3<異文化接触の意義>
3 次の文章を読み,下の問い(問1~6)に答えよ。
かつて人類学者のマルセル・モースは,次のように語ったと言われる。「戦士の服にすっかり身を包んでいた捕虜ジャンヌ・ダルクが女であることを,イギリス人たちはどうしてさとったのか。彼女は腰かけていた。誰かが彼女の膝の上に胡桃を投げたのだ。それを落とさないように,彼女は両膝をすばめるかわりに広げたのだ。あたかも着けていたロング・スカートをぴんと張るためであるかのように。」
この話は何を示しているのだろうか。ある状況での個々人のなにげない身振りやしぐさ、立ち居振る舞いには意味があり,それは A に基づいて解読することができるということである。私たちのこのような振る舞い方の多くは,本能などによる生得的なものではなく,それぞれが属する社会の中で,他の人々との相互作用を通して習得された慣習なのである。しかも,それらは個々人の内にいわば血肉化されている。このことは,振る舞い方に限られるわけではない。私たちが常識と呼ぶ社会的規範もこうして習得された慣習から成り立っている。さらには,虹がいくつの色から構成されていると見るかは文化や社会によって異なっているように、a私たちの知覚のあり方も、それぞれの文化や社会の影響を強く受けて形成されているのである。しかし,このことを私たちは通常意識せず,慣習や常識をあたかも普遍的なものとして受け入れがちであり,それらによって社会の安定も維持されている。そして,ここには,どのような行動の仕方や考え方が B であるかについての共通の理解が成立している。しかも、bこうした慣習や常識は,社会の安定のために,それらにそぐわないものに対して,社会的な逸脱者というレッテルを貼ろうとするのである。
このように,私たちの社会的な制度や文化の構造は,慣習や常識によって歴史的に推持されてきたが,このことは時として,自分の文化を自明視して他者に強要する頑なな態度ともなり,異文化との悲惨な衝突を引き起こした。それだからこそ,異なった慣習や常識をもつ文化や社会との接触の機会がますます増大している昨今,私たちは、cその接触の場面において,それぞれの文化や社会における慣習や常故の間の軋轢やそれらの無自覚的な押しつけの危険性があることに,以前にも増して注意を払うべきである。それによって,自らの慣習や常識を見直すことにもなるのである。この場合,異文化とは外国文化に限らない。例えば,世代間や男女間でも文化的慣習の衝突や軋轢があることを見落としてはならない。現在,冷戦終結後の国際関係の中でナショナリズムの台頭が懸念され,また,高齢化社会のあり方やセクシュアル・ハラスメントが問題となっていることを考えても,こうした文化や社会の接触がもつ意味の重要さを私たちは常に顧慮する必要があるのである。
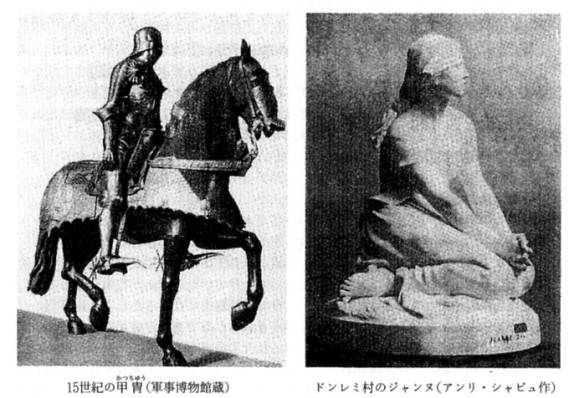
問1 文中の A に入れるのに最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 1
① 歴史を通じて美的に洗練されたモード
③ 社会的に共有されたコード
問2 文中の B に入れるのに最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 2
① 観念的 ② 合理的 ③ 主体的 ④ 超越的
問3 下線部aに関連して,個人のパーソナリティにもこうして形成される面がある。パーソナリティに関する現代の思想家の見解についての記述として最も適当なもの
を,次の①~④のうちから一つ選べ。 3
① フロイトは,パーソナリティが乳幼児期の体験で形成されるとは考えず,社会経済的条件やイデオロギーなどの要因と個人の諸欲求との相互作用によって形成されると主張している。
② リースマンは、他人の行動に照準を合わせて自己の行動を決定していくパーソナリティを「他人指向型」と呼ぶが,現代の大衆社会では個々人が自己閉塞的になり,このような性格は見られなくなったと主張している。
③ フロムが「社会的性格」と呼ぶものは,一つの集団や階層文化に属する諸個人の大部分がもつパーソナリティ構造の中核を意味し,それは,集団等に共通の基本的体験や生活様式によって形成されるものである。
④ アドルノが「権威主義的パーソナリティ」と呼ぶものは,民主主義を否定して,非合理的な扇動や権威によって国民を強力に統率する性格類型を意味し,それは,ファシズムの指導者に顕著に見られるものである。
問4 下線部bに関して,このような社会的な逸脱についての記述として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 4
① 常識は科学的な中立牲と客観性とをもった公正な基準であり,それに基づけば、社会の発展にとって有用で創造的な活動を行うことができない人は逸脱者として規定されることになる。
② 常識からの逸脱と見られる行動は,ともすると,それを行う人の生まれつきの素質によると考えられやすく,社会そのものがそれを作りだす面のあることは気づかれにくい。
③ さまざまな欲求にかりたてられ,葛藤や欲求不満におちいりやすい青年の行動には社会生活に不適応な面があるとしても,現代社会では,その行動は常識から逸脱したものとみなされることはない。
④ 法律は暗黙に受け入れられている社会的慣習を明文化したものであるから,法律に従って生きてさえいれば,社会からの逸脱者というレッテルを粘られることはない。
問5 下線部cに関して,このような軋轢や押しつけの危険性を示している事例として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 5
① 外国に工場を作った日本のある企業では,地元の労働力に期待しながらも,日本式の雇用形態や管理の仕方を採用したため,雇用者側と被雇用者側との意思の疎通に問題が生じた。
② 日本の学校の授業では,黙って先生の話を聴くことが優先されるため,自己主張や積極的な発言が当然のこととみなされている国からの帰国子女の一人は,他の生徒たちからいじめられ,話さなくなってしまった。
③ 「以心伝心」と言われるように,日本では言葉によらない意思の疎通が重視されるため,「気が利く人」の評価が高い。ところが,外国から来た同僚は言葉で指示されないと動かないので,人物評価が下がってしまった。
④ 日本のように新年に年賀状を出す習慣が相手の国には存在しないという理由から,外国に多くの知人をもつある人は,クリスマスカードは出すが,日本式の年賀状は遠慮して出さない。
問6 文化に対する見方として,本文の趣旨に合致しないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 6
① それぞれの文化は,それに特有な慣習や常識を後続の世代に伝授し,学習させることによって,再生産されてはいるが,異文化における慣習や規範に対して常に開かれている柔軟なものであるべきである。
② 文明化や工業化など、近代西欧社会をモデルにした概念によって,西欧以外の社会や文化を発展史的に位置づける文化理解の方法は容易に払拭されえないが,この方法はそのままの形で維持されるべきではない。
③ 自文化の外部に目を向けてカルチャー・ショックを受けた場合,自文化と異文化とを比較して,文化間に優劣をつける態度が生じやすいが,これは,多様な文化が共存するためには望ましいものではない。
④ 世代には世代特有の,男性には男性,女性には女性特有の,歴史的に育まれてきた考え方や行為の仕方があるとしても、社会や文化の維持、存続に役立つものが優先されるべきである。
〔12-追〕