|
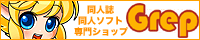

零 戦~Wing of Dreams~
【零戦52型】 1995,5/03,茨城県竜ヶ崎飛行場 撮影:あおいしんご
“叶うことで失う夢と、夢のままで終わる夢と、どちらが幸せなのだろう…?”
かつて恋い焦がれた零戦の飛翔を目の当たりにしながら、私はぼんやりと
そんなことを考えていた‥。
健全に育った少年達なら皆、身に覚えのあることだが、“早くて格好良い乗り物”は
憧れの対象なのだ。人によってはそれがサンダーバード2号であったり、
或いはランボルギーニ・カウンタックLP400であったりするだろう。
子供の頃の私にとって『零式艦上戦闘機=零戦』は、真にそうした存在であった。
ジュブナイル版『大空のサムライ』(注1)に感化されたか、少年ジャンプの
『ゼロの白鷹』(注2)の影響であったか、今となっては思い出せないが、とにかく
無邪気な憧憬と、ある種の畏怖の念が入り混じった崇拝の対象だった事は確かだ。
「初陣であった重慶上空の空中戦では、敵機27機全機を撃墜した。」
「〝ゼロファイターに遭ったら逃げろ!〟
アメリカ軍は零戦の強さに恐怖した。(注3)」
「単座機の常識を打ち破る航続力と世界一の格闘性で、
巴戦では無敵だった。」
プラモデルの説明書に謳われたこれらの文句を、何か我が事の様に誇らしく感じていた…
初めて本物の零戦と対面したのは、中学生になってからだと記憶している。
場所は上野の国立科学博物館。此の地に零戦が一機、展示してあることは書物からの
知識で知ってはいたが、学校の社会科見学か何かで上野動物園を訪れた際、
引率の教諭に無理を言って見学コースに加えてもらったのだった。

「…でっかいなぁ。」
同級生が洩らしたこの一言は周囲の失笑を買ったが、実のところ私自身も、
胸の中でまったく同じ事を考えていた。全長9.05m、全幅12m、自重約1.6t という
基本データぐらいは当然、頭に刻み込んでいたのだが、いざ実物を前にすると
“こんなに大きいのか…?”という驚きとともに、ジュラルミンと鋼鉄、それに幾らかの
アクリル板で出来た「兵器」であることを、否が応でも実感させられてしまった。
しかも、この機体は撃ち落とされ、朽ち果てようとしていた物を回収し、復元した姿なのだ。
幾つも作ったプラモデルと同様、優美なラインを持つこの飛行機が、同時にかつて
この機を駆って戦った者にとっては棺桶であるという事実(注4)に、私は少なからず困惑
していた。間違っても“カッコイイ”などという言葉は出てこなかった。
「防弾装備はまったく考慮されておらず、守勢に廻ると脆弱であった。」
「零戦を徹底的に研究したアメリカ軍は
続々と新型機を繰り出し、数で圧倒していった。(注5)」
「制空戦闘機としては時代遅れとなった後は、
特攻機として多くが散華した…。」
各型合計の総生産機数は10,430機。終戦時の残存機は1割にも満たない。
もちろん、喪われたのは機体だけではない。若きパイロット達もまた‥
戦争とは、究極の浪費である…。
それでも、零戦はまだ恵まれた余生を送っていると言えるかもしれない。上野の他にも
日本各地に復元され、往時を偲ぶ姿で保存されているものが幾つもあるからだ。
まだ10代の頃、それらの何機かを拝観する機会を得たが、展示機はすべて“死んだ”
状態であり、映像を通してしか“空を飛ぶ”零戦を知る術はなかった。(注6)
大学生活の後半、私はある大それた目的のために落とせる単位は全部落として、
ひたすらアルバイトに精を出していた。その目的とはズバリ “零戦に乗ること”。
少し説明すると、先ず渡米して民間のパイロット学校に入り免許を取る。その後に
フライアブルな零戦を所有する団体を(注7)訪れ、「零戦に乗せてくれませんか?」と
頼み込み、実際にこの手で飛行させてみたかったのだ。
厚かましい上に無謀なこの計画の成功率はきわめて低かったが、まだ若くて充分に
脳天気だった私は、“行けば何とかなるさ” ぐらいにしか考えていなかった。
結局のところ、諸事情により(注8)、恥ずかしながら実現には至らなかったが…
夢は夢として胸に秘めたまま、私は社会人となり、通勤電車に揺られる日々が始まった。
何年かが経ち、名刺に某かの肩書が付く頃になって“零戦、17年振りの飛来” の報を知り、
いてもたっても居られなくなった私は、会場である茨城県竜ヶ崎飛行場へ出向いていた。
生まれて初めて“生きた” 零戦を見られるのだ。これを逃す手はない。
‥それは冗長なショウだった。主役のはずの零戦は滑走路の隅にぽつんと駐機したまま。
主催者側が用意した観客席は、前日の雨でぬかるみと化した只の芝生。前方に陣取った
マニア連中は好き勝手にカメラの三脚を立て、彼等ですら延々と続くヘリと複葉機の
アトラクションにいい加減うんざりしている様子が観てとれた。
―ようやく、零戦のエンジンに火が入り、観客席も生気を取り戻した。―

「…ポンコツだなぁ。」
ギャラリーの何者かが不作法にも洩らしたこの一言に、誰も反論できなかった。
暖機運転のあいだ中、零戦のエンジンは今にも止まりそうな頼りない音を発したのである。
ひとたび大空に舞い上がってしまえば、それはもう軍用機とは思えない程の軽やかな
機動ではあったが、エンジンの推力を絞っての飛行であることは明らかだったし、
併走する“駿馬” P51マスタングに比べると、コンディションの差は歴然としていた。
61-120号機は“老骨に鞭打って” 演技を見せているように思えて仕方なかったのだ。

“人が老いてゆくように、飛行機もまた年老いてゆく…”
この単純にして残酷な事実を、私は受け容れるしかなかった。もし私が目論見通りに
零戦の操縦席に座れる身となっていたら、どのような感慨を持ったであろうか?
デモフライトを終え、凹凸の目立つ外板を晒しながら駐機エリアへタキシングしてゆく
零戦を見送りながら、その機会が訪れなかった事を、秘かに感謝したい気分だった。
“叶うことで失う夢と、夢のままで終わる夢と、どちらが幸せなのだろう…?”
その後も何度か、零戦を故国で飛行させる試みが現れては消えていった。(注9)
現在の私はそのことを、失望2割、安堵8割ぐらいの気分で受け止めている。
願わくば、現存するすべての零戦たちに、安らかな余生を過ごして欲しいと思う‥。
※大戦機の復元、飛行に尽力される方々を批判するつもりは
一切ございません。念のため。
(注1) もはや説明の必要が無いほど有名な同書に、映画版『大空のサムライ(’76,東宝)』のスチール写真を挿絵
代わりに使い、平易な文書に書き換えたジュブナイル(子供向け)版があったことは、意外に知られていない。
(注2) 本宮ひろ志氏が’76~77に描いた珠玉の戦争マンガ。若き零戦乗り達の喜び、悲しみ、憤りが氏の迫力ある
筆致によってダイレクトに伝わってくる。未読の方は是非!
(注3) 正確には〝Do not dogfighting with ZERO.(零戦と格闘戦を行うべからず)〟であり、高速&大馬力を
活かして戦うよう指示したもの。決して敵前逃亡の推奨ではない。
(注4) 昭和20年1月9日、アドミラルティ諸島偵察行で未帰還となった253空所属、吉沢徳重上飛曹のものと推察
される遺骨を、この零戦を引き揚げたB・コラン氏が丁重に埋葬したそうである。‥合掌。
(注5) グラマンF6F“ヘルキャット”の試作指示は’41年6月、原型初飛行は’42年6月。零戦を念頭に置いて設計
された訳ではないが、“F4Fのインプルーブド版を作る”という米海軍の目論見は正鵠を得ていた。対する
日本海軍の後継機“烈風”は’42年7月試作指示、原型初飛行は’44年5月 。すべてが遅すぎた…。
(注6) 映画 『パール・ハーバー(’01,米)』について一言。レシプロ機版 『インディペンデンス・ディ』だと割り切って
しまえば腹も立たないが、サイパン島で捕獲された零戦52型と、ニューギニア島の残骸から復元された
零戦22型が揃ってハワイの空を飛んだという事実には、やはり運命の皮肉を感じずにはいられない。
(注7) 当時(今でも)知られていたのは、カリフォルニアにある“プレーンズ・オブ・フェイム”(零戦52型所有)および
テキサス州の“コンフェデレート・エア・フォース”(零戦21型所有)。いずれにしても、何処の馬の骨とも
知れない日本人に、零戦の操縦桿を任せたとは思えない。若さ故の思い込みである。
(注8) 資金と語学力の不足の他に、単位を落とし過ぎて卒業が危うくなったことが最大の原因だった…。面目ない。
(注9) 1995年にはハワイから島伝いに8,600kmの洋上飛行で日本を目指すという“プロジェクト・テイクオフ”が
2001年には南紀白浜で欧米並みの一大航空ショウを開催しようという“ジャパン・エアショー2001”が
それぞれ計画されたが、経済的、外因的理由によって実現には至らなかった…。
日本各地の零戦観てある記‥?
『零戦たちとの邂逅(かいこう)』はこちらをClick!
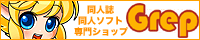
|





