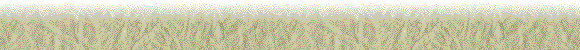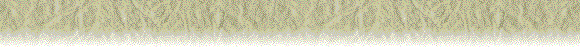
c-Two-Way tossインターネットランドへ戻る
授業・教科/国語/中学校全学年/詩/分析批評
【答え】 かなしみはあたらしい(谷川俊太郎)
| 1-1 生徒それぞれの発想でよい。詩人の「あたらしい」というとらえ方の新鮮さに注目させるための問い。以下、生徒の発表から。 ・かなしみは(正直者にさせる) ・かなしみは(パンドラの箱である) ・かなしみは(贈り物である) ・かなしみは(怒りの一部である) ・かなしみは(電車のようなものである) ・かなしみは(みんなの・・・) ・かなしみは(無邪気である) ・かなしみは(心の中の大切な宝物が壊れて、ショックを受けて泣いてしまうことである) 1-2 この段階では、まだ詩の読解に入っていない。その前に、「あたらしい」とは、何を言いたいのか、生徒に予想を立てさせる。以下、生徒の意見は、大きく二つに分かれた。 ・なまなましい? ・悲しいことの直後? ・みずみずしい? ・新鮮? 2-2 「全部ひらがなだ」「子どもが大人に文句言っているみたい」など、核心に触れる疑問・意見が、あらかた出る。また、出来るだけ出させる。 2-3 ・以下は生徒の発言。()内は作成者の注。 ・漢字だと固い感じがするけど、ひらがなだと柔らかい感じがする。 ・漢字で書かれたものは、大人の文みたい。ひらがなだから、ああ、子どもが言っているんだなあ、ってわかる。(なるほど!と思った。確かに、漢字仮名交じりのものは、きつい抗議文のようだ。漂うかなしみや情感は、ひらがなだからこそのものだと気づいた。) ・ひらがなは、読みにくい。(「だから読み手は、じっくり読みとろうとするのかもしれないね」と教師が助言を入れた。「あっそうか!」という声があがる。) 2-4 「あなた」と「わたしたち」。 2-5 「わたしたち」が、「あなた」に向けて語っている。 2-6 <板書> 「わたしたち」=子ども、「あなた」=大人。 「・・・・てください」という丁寧な口調、「あなどらないでください」という表現から、年齢の開きや上下関係がわかるようになっている。また、「わたしたちはあなたのように/つかれてはいないから」を根拠にあげた生徒もいた。「つかれているのは大人だから」とのこと。お見事! 2-7 <板書>語り手(子ども):「あなた」に何かを言いたい。 ・目をそらさないで ・あなどらないで ・あなたと同じと思わないで 「あなた」(大人):子どもを馬鹿にしている。疲れている。 *黒板を上下2段に分け、上に語り手(こども)、下に「あなた」(大人)に関するものを書く。 2-8 「あなた」の、「わたしたち」を馬鹿にした態度。分かってくれない態度。この発問は、2-10につながってゆく。 2-9 <板書>語り手(子ども):かなしみは よろこびも →あたらしい いかりも と書いてから問う。「よろこび」「いかり」が加わることで、生徒は次の結論を出す。 ・「あたらしい」とは、「(すべてが)その都度違う、色々な体験」ということ。 発問1-2より、読みが深まっている(また、深まるようにしたい)。また、「大人の方は?」と聞いてみると、次のような答えが返ってきた。 <板書>「あなた」(大人):かなしみは →ない。考えたくない。考えてもしょうがないと思っている。 このように、大人と対比することで、生徒は、「あたらしい」の意味するものに、より迫れたようだ。 2-10 「わたしたち」の気持ちを分かってほしい。 3-1 ここまでの読解と矛盾するかもしれないが、正解は、「わからない」。子どもである「わたしたち」の言い分が述べられているだけで、大人側の「あなた」の言い分は載っていないから。 3-2 (例)傷つきやすい。感受性が強い。繊細。ひょっとしてわがままかも? 分かってほしいということは、あきらめていないということ?等。 この詩は、自我の芽生えた「わたしたち」から、無理解な大人(と想像される)の「あなた」への、異議申し立てという形をとっている。しかし、単なる反抗、抵抗ではなく、その底に、多感さや傷つきやすさ(傷つけやすさにもなりうるが)を持つ、思春期の少年少女の姿が透けて見えるようになっている。ここでは「わたしたち」の人物像を、多面的にとらえてもらえれば良いのではないか。 |
|
|
メール |
表紙へ戻る |
神奈川県立向の岡(むかいのおか)工業高等学校定時制