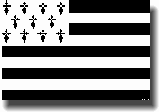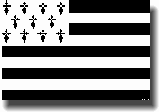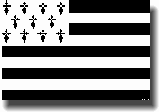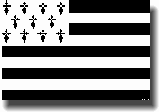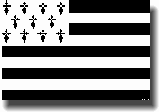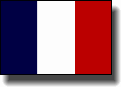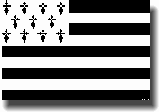ブルターニュの地理
ブルターニュ地方はフランスの最西部、北、西、南の三方を海に囲まれた半島に位置しています。
面積は約27,000平方メートル。日本の岩手県と秋田県を合わせた面積に相当する広さなのだそうです。人口は約280万人で、イール・エ・ヴィレーヌ、モルビアン、コート・ダルモール、フェニステールの4つの県から成っています。フランスの一部でありながら、ケルト文化が現在まで息づく地方です。かつてはブルターニュ公国として、フランス国王の廷臣でありながらブルターニュ公爵を中心に独立国に近い権勢を誇っていました。 |
ブルターニュの歴史
ブルターニュにケルト人が定住し始めたのは、およそ紀元前6世紀ごろのことだそうです。その後やっって来たローマ人の支配下に組み込まれガロ=ローマと呼ばれる期間が500年ほど続きます。現在まで続くブルターニュのケルト文化を決定付けたのは、5世紀半ばごろにイギリスのコーンウォール半島からこの地にやってきたケルト系ブルトン人でした。5世紀頃のヨーロッパは、アングロ=サクソン族がヨーロッパのあちこちに国を打ち立てた時代です。彼らの侵入は、栄華を誇った西ローマ帝国は滅亡させただけでなく、イギリスにいた先住のケルト系住民たちをコーンウォール半島やウェールズといった西の端へと追い詰めていました。行き場を失った彼らが船に乗ってブルターニュへと渡り、約200年間に渡って定住していったのが、ブルターニュがフランスの一部でありながらケルト文化が現在まで息づく地方になった由来です。 |
6世紀ごろにフランスにやってきたゲルマン系フランク族との長い戦いの末、824年ブルターニュ地方はとうとうフランク王国に征服されてしまいます。このとき、フランク王国の国王ルイ敬虔王は生粋のブルトン人であるヴァンヌの土豪ノミノエにブルターニュ公の称号を与え、ブルターニュ地方の統治を任せたのがブルターニュ公国の始まりです。12世紀には、イングランド王ヘンリー2世の“アンジュー帝国”の一部に組み込まれ、一時的支配を受けます。波乱続きのブルターニュ公国ですが、それでもフランスやイングランドといった外敵から何とか独立守り続け、運命の16世紀を迎えます。1532年、フランス国王フランソワ1世の王妃であり、最後のブルターニュ公女となったクロードが亡くなると、後継者を失ったブルターニュ公国はフランス国王の下に統合され、ついに700年に及ぶ歴史に幕を下ろしてしまったのでした。 |
ブルターニュとフランス革命
ブルターニュ人は、概して信心深く純粋で保守的な人だそうです。彼らのブルターニュ気質が悲劇へと結びついてしまったのが、18世紀後半に起こった反乱でした。1789年に始まったフランス革命期、カトリックの僧侶への迫害、教会財産を国有化する法律の制定、国王ルイ16世の処刑、外国勢力と戦うための農民徴兵の宣告などなど、数々の新体制を打ち出したフランス革命政府に対し、始めは革命政府の動きに同調していたブルターニュは、次第に反革命政府への動きを強め、ついに武装蜂起を引き起こします。ふくろう党の反乱といわれるこの蜂起には、フランスの旧貴族たちだけでなく、神や国王、司祭や領主を敬うブルターニュの農民たちも数多く加わっていました。反乱は革命政府が送り込んだ軍によって壊滅しますが、ブルターニュ全土での犠牲者は十数万人ともいわれ、その後のブルターニュに反中央意識を植え付ける要因になったそうです。私たちが教科書で習うフランス革命は、民衆が自由を勝ち取ったのいかにも素晴らしい出来事のようですが、急進的な人々によってフランスが支配された革命後期の歴史は恐怖政治とも呼ばれ、真っ向から立ち向かった人々が弾圧を受けたということもまた事実なのです。 |
ブルトン語
ブルターニュでは、ブルトン語と呼ばれるケルト語が現在でも話されています。5世紀半ばごろからこの地にやってきたブルトン人の話し言葉が今日のブルトン語の基となっており、コーンウォール語(16世紀に消滅)やウェールズ語と同じブルトン語群に属します。ブルターニュ地方西部へ行くほど、ブルトン語を耳にすることが多くなります。ブルターニュで私がブルトン語を聞いたのは数回ほどですが、ケルト語はほとんど覚えのない耳には、発音やイントネーションは魔法の呪文のように聞こえました。ケルトは魔法や妖精の宝庫ですものねぇ。聞いた話だと、現在でも片方がブルターニュ語を話し、もう片方がウェールズ語で会話をすれば、お互いになんとなく理解し合えるのだそうです。この話が本当なら、1500年もの昔にイギリスからこの地に多くの人々が渡ってきたという歴史の生きた証拠ですね。ホントにすごい!! |