かつてのノルマンディーとブルターニュの国境地帯近くにそびえるモン・サン・ミシェルです。陸地から約2キロほど離れた海上の岩山にそそり立つ修道院は、かろうじてノルマンディー地方に属しています。世界遺産にも登録されているモン・サン・ミシェルは、日本でも人気の高い観光スポットなので、ご存知の方も多いはずです。
モン・サン・ミシェルがある岩山には、大昔からガリア人やローマ人が神殿を建てていたそうですが、モン・サン・ミシェルの起源は8世紀にさかのぼります。モン・サン・ミシェルから車で30分ぐらい行った所にある町アヴランジュの司教であったオベールの元に大天使ミカエル(仏語でサン・ミシェル)が現れ、この岩山の上に自分に捧げる聖堂を建てるように、と彼に命じたのだそうです。そのとき建てられたのは小さな祠だったそうですが、こんな絶海の孤島で修行に励んだ僧達の生活とは、いったいどんなものだったのでしょうね。
10世紀に時のノルマンディー公リシャールがベネディクト会の修道院を設立して以降、モン・サン・ミシェルの発展が本格的に始まります。何度も増改築が繰り返され、13世紀に修道院は島を取り囲む海の特性を利用して城塞化します。モン・サン・ミシェルをぐるりと囲むモン・サン・ミシェル湾は、満潮時と干潮時の潮の差が最大14メートルにも達し、干潮時には沖合い15キロまで砂地が露出します。反面満ち潮の時には、驚異的なスピードで海水が上がってくるそうで、海と絶壁に守られたモン・サン・ミシェルはまさに天然の要害として、難攻不落と称えられる城塞修道院となりました。英仏間で戦われた百年戦争ではイングランドの攻撃を受けますが、決して敵の手に落ちなかったそうです。
しかし、すさまじい潮の流れは迫りくる敵を撃退するのには大変有効ですが、モン・サン・ミシェルが巡礼の中心地として栄えていた中世時代、はるばる修道院までやってきた巡礼者たちが数多く潮の流れに飲み込まれ、溺れ死んでしまったという悲しい一面もあります。私がモン・サン・ミシェルを訪れたときは干潮時だったので、白い砂地がむき出しになり、海水ははるか彼方に見えるだけでした。延々と続く砂地に下りて歩いてみようかな?とちらりと思ったのですが、万一満ち潮に追いかけられる事を想定して、怖くて下りることができませんでした。でも、高台から眺めたモン・サン・ミシェル湾の日の入りは、とても幻想的で息を呑むほど綺麗だったです。
11世紀の建立以来、一度も外部からの攻撃によって落ちたことのなかったモン・サン・ミシェルですが、フランス全土で革命の嵐が吹き荒れた18世紀後半、ついに革命政府の元に陥落となります。敵の襲撃を何百年にも渡って防ぎ続けた要塞は、今度は脱獄不可能な牢獄へと転用され、多くの反革命政府の囚人たちが収容されることになりました。広大な領地を持ち繁栄を誇ったモン・サン・ミシェルなのに、現在修道院の内部ががらんとしているのは、この時代のせいです。高価な調度品や貴重な文化財などは、モン・サン・ミシェルが略奪の憂き目にあった際に持ち出されてしまったのだそうです。内部には聖堂を始め多数部屋がありますが、ほんとに空気以外何もない空間が続いていました。
19世紀の後半、ようやくモン・サン・ミシェルは牢獄の役目から解放され、現在のような国立博物館へと生まれ変わりました。20世紀に入ると修道院も再開され、内部の聖堂ではミサも行われているそうです。いったいどんな修道士さんたちがこの地で生活をしているのでしょうね。
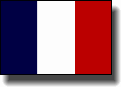 |
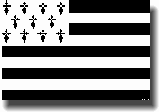 |
| フランスに戻る | ブルターニュに戻る |