お知らせと議事録がご覧になれます。


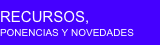
議事録
| ここでは、これまでに開催されたTADESKAの議事録や活動内容をご覧になれます。 |
| 開催日 | テーマ | ||
| 第1回 | 2006年4月15日 | 発足に当たって。運営方針や活動内容の確認 | |
| 第2回 | 2006年5月13日 | モチベーション (1) | |
| 第3回 | 2006年6月10日 | モチベーション (2) | |
| 第4回 | 2006年7月8日 | モチベーション (3) ブレーンストーミング | |
| 第5回 | 2006年9月11日 | クラス内での学力差 (1) | |
| 第6回 | 2006年10月14日 | クラス内での学力差 (2) | |
| 第7回 | 2006年11月11日 | 教材 (1) 教科書の使用例・感想など | |
| 第8回 | 2006年12月9日 | 教材 (2) 理想の教科書 | |
| 第9回 | 2007年2月10日 | 教材 (3) 補助教材 | |
| 第10回 | 2007年3月13日 | 特別教室(LL教室,CALL教室など)での機材を用いた授業実践 | |
| 第11回 | 2007年4月14日 | メソッド(1) 文法訳読法について |
|
| 第12回 | 2007年5月12日 | メソッド(2) パターン練習を中心に |
|
| 第13回 | 2007年6月9日 | メソッド(3) コミュニケーションに根ざした教授法 |
|
| 第14回 | 2007年7月14日 | メソッド(4) 最新の教授法理論と教授法の総括 |
|
| 第15回 | 2007年9月8日 | 文法事項の教え方(1) 時制 | |
| 第16回 | 2007年10月13日 | 講読会:講読会:Ellis, Rod (1999). Second Language Acquisition: Oxford. Oxford University Press 第1,2章 | |
| 第17回 | 2007年11月3日 |
クラスマネージメント |
|
| 第18回 | 2007年12月1日 | 講読会:Ellis, Rod (1999). Second Language Acquisition: Oxford. Oxford University Press 第2,3,4章 | |
| 第19回 | 2008年2月2日 | 文法事項の教え方(2)「冠詞の教え方」 | |
| 第20回 | 2008年3月1日 | 講読会:Ellis, Rod (1999). Second Language Acquisition: Oxford. Oxford University Press 第4,5章 | |
| 第21回 | 2008年4月5日 | 文法事項の教え方「冠詞」(2) 教材作成の試み | |
| 第22回 | 2008年5月10日 | 講読会:Ellis, Rod (1999). Second Language Acquisition: Oxford. Oxford University Press 第5,6章 | |
| 第23回 | 2008年6月7日 | 教師の専門性を授業にどう活かすか (1) | |
| 第24回 | 2008年7月6日 | 日本の大学におけるスペイン語の教科書のあり方(特別企画) | |
| 第25回 | 2008年10月4日 | 教師の専門性を授業にどう活かすか(2) | |
| 第26回 | 2008年11月1日 | 講読会:Ellis, Rod (1999). Second Language Acquisition: Oxford. Oxford University Press 第6章 | |
| 第27回 | 2008年12月6日 | 教師の専門性を授業にどう活かすか(3) | |
| 第28回 | 2009年2月7日 | 講読会:Ellis, Rod (1999). Second Language Acquisition: Oxford. Oxford University Press 第7章 | |
| 第29回 | 2009年3月7日 | 教師の専門性を授業にどう活かすか(4) | |
| 第30回 | 2009年4月4日 | あなたの意見では接続法をどの段階で教える? | |
| 第31回 | 2009年5月2日 | 中上級にふさわしいタスクとは | |
| 第32回 | 2009年6月6日 | 授業において学生が感じる心理的負荷 | |
| 第33回 | 2009年7月4日 | CALLを利用せずに『コミュニカティブな』授業をめざすには | |
| 第34回 | 2009年9月5日 | 第二外国語としてのスペイン語教育で効果的な小テストと課題について< | |
| 第35回 | 2009年10月3日 | 初習学習者への発音、音節、強勢の指導法について | |
| 第36回 | 2009年11月7日 | 講読の授業を単なる文法訳読の授業にしないための工夫 | |
| 第37回 | 2009年12月5日 | 留学生へのスペイン語教育について | |
| 第38回 | 2010年2月18日 | 関西スペイン語教師の集い | |
| 第39回 | 2010年4月3日 | 初級第2外国語スペイン語授業における練習問題について | |
| 第40回 | 2010年5月8日 | 初習者のより効果的なスペイン語学習のために 教師としてどのような工夫やアドバイスができるか | |
| 第41回 | 2010年6月5日 | Plan Curricular del Instituto Cervantes(PCIC)を利用したA1-A2 レベルのコースデザインの試み | |
| 第42回 | 2010年7月3日
論文要約 |
スペイン語教師としての私達の実践についてふり返る | |
| 第43回 | 2010年9月11日 | スペイン語のSER、ESTAR、HAYの学習について | |
| 第44回 | 2010年10月02日 | スペイン語の授業における試験の作成について | |
| 第45回 | 2010年11月06日 | 冠詞の機能を習得し、使用できるようになるために必要な(初級の段階での)説明・用例・使用経験 | |
| 第46回 | 2010年12月04日 | 初級スペイン語クラスにおいて接続法をどう扱うか | |
| 第47回 | 2011年2月6日 | 関西スペイン語教師の集い | |
| 第48回 | 2011年3月5日 | モチベーション | |
| 第49回 | 2011年4月9日 | GIDEシンポジウムの報告「高校の授業について」 モチベーション−教材の観点から |
|
| 第50回 | 2011年5月7日 | モチベーション - 新しいツールの観点から | |
| 第51回 | 2011年6月11日 | エラーを扱いつつ、いかに学生のモチベーションを維持するか | |
| 第52回 | 2011年7月9日 | 教室でスペイン語を媒介言語として使用することはモチベーションを上げるか? | |
| 第53回 | 2011年9月3日 | 『スペイン語新文法(Nueva gramatica de la lengua espanola)』 序文抄訳(suspendido中止) |
|
| 第53回 | 2011年10月1日 | 『スペイン語新文法(Nueva gramatica de la lengua espanola)』 | |
| 第54回 | 2011年11月5日 | 『スペイン語新文法(Nueva gramatica de la lengua espanola)』 | |
| 第55回 | 2011年12月3日 | 『スペイン語新文法(Nueva gramatica de la lengua espanola)』 | |
| 第56回 | 2012年2月19日 | 関西スペイン語教師の集い | |
| 第57回 | 2012年3月3日 | 色弱(Daltismo)の学習者はどのように見えているか | |
| 第58回 | 2012年4月7日 | スペイン語を教える教師のモチベーション | |
| 第59回 | 2012年5月12日 | 20分で一つの文法事項を教える提案 | |
| 第60回 | 2012年6月2日 | 品詞体系と語学教育 | |
| 第61回 | 2012年7月7日 | ラーニング・ポートフォリオの活用 | |
| 第62回 | 2012年9月8日 | TADESKAの歩みと今後 | |
| 第63回 | 2012年10月6日 | スペイン語の授業を有意義なものにするために | |
| 第64回 | 2012年11月17日 | Actividades del dia a dia | |
| 第65回 | 2012年12月1日 | 教材研究‐テキスト『Encuentro con el mundo del espan~ol (1)』 の授業の進め方とイラストシートの使い方の考察 | |
| 第66回 | 2013年2月10 日 | 第4回関西スペイン語教師の集い | |
| 第67回 | 2013年3月2日 | テーマ1:「第4回関西スペイン語教師の集い」テーマのふりかえり
テーマ2:2013年度の活動の計画-所要時間20分の教案を作る企画 |
|
| 第68回 | 2013年4月6日 | テーマ1:所要時間20分の教案を作るー名詞句
テーマ2:TADESKAの運営方法について |
|
| 特別会 | 2013年5月10 日 | Tres enfoques para la integracion de las TIC en el aula de idiomas | |
| 第70回 | 2013年7月6日 | 所要時間20分の教案を作るー目的格人称代名詞 | |
| 第71回 | xxxxx | ||
| 第72回 | 2013年9月7日 | 所要時間20分の教案を作る − 語順 | |
| 第73回 | 2013年10月5日 | 生教材を準備する | |
| 第74回 | 2013年11月2日 | 所要時間20分の教案を作る-点過去規則型の活用習得 | |
| 第75回 | 2013年12月7日 | 所要時間20分の教案を作るースペイン語の読み方・発音 | |
| 第76回 | 2014年2月9日 | 第5回関西スペイン語教師の集い | |
| 第77回 | 2014年3月1日 | 第5回関西スペイン語教師の集いで扱ったテーマのふりかえり | |
| 第78回 | 2014年4月5日 | 所要時間20分の教案を作る - gustarと同じように用いられる動詞 | |
| 第79回 | 2014年6月7日 | 発音を教えるためのヒント | |
| 第80回 | 2014年7月5日 | プロジェクターで使える教材と所要時間20分の教案を作るー基数詞 | |
| 第81回 | 2014年9月6日 | 所要時間20分の教案を作る 再帰動詞:その導入 | |
| 第82回 | 2014年10月04日 | 所要時間20分の教案を作る-ジェスチャーゲーム, 初級レベルスペイン語学習者向けスペイン語ポライトネスの入門 | |
| 第83回 | 2014年11月1日 | 所要時間20分の教案を作る 点過去と線過去の使い分け | |
| 第84回 | 2014年12月6日 | 所要時間20分の教案を作るー授業を始めるための質問 | |
| 第85回 | 2015年2月8日 | 第6回 関西スペイン語教師の集い | |
| 第86回 | 2015年3月7日 | 「第6回関西スペイン語教師の集い」で扱ったテーマのふりかえり | |
| 第87回 | 2015年4月4日 | 日本の大学におけるスペイン語教育の制度的条件と環境 『スペイン語新文法(基礎編)』 第1章『導入』第1節『文法』 |
|
| 第88回 | 2015年5月9日 | 「日本の大学におけるスペイン語教育の制度的条件と環境(2)」 『スペイン語新文法(基礎編)』 第2章『語』形態論-第2節『性』 |
|
| 第89回 | 2015年6月7日 | 日本の大学におけるスペイン語教育の制度的条件と環境(3) 『スペイン語新文法(基礎編)』第3章 『語』 2a 形態論 第3節 『数』 |
|
| 第90回 | 2015年7月4日 | 「日本の大学におけるスペイン語教育の制度的条件と環境(4)ー制度の変遷」 『スペイン語新文法(基礎編)』 第II章 『語』 IIa 形態論 第4節 『動詞の屈折』 pp.31-43」 |
|
| 第91回 | 2015年9月5日 | 『スペイン語新文法(基礎編)』第II章『語』IIa 形態論 第5節『派生と複合』 TADESKA紹介ワークショップの予行演習 |
|
| 第92回 | 2015年10月3日 | 『スペイン語新文法(基礎編)』第II章『語』IIa 形態論 第6節『名詞』 「日本の高等学校におけるスペイン語教育の制度的条件と環境」 |
|
| 第93回 | 2015年11月7日 | 「日本の大学におけるスペイン語教育の制度的条件と環境-新しい時代のスペイン語教師のあり方を考える」 『スペイン語新文法(基礎編)』第8節 『限定詞と代名詞』』 |
|
| 第94回 | 2015年12月5日 | 「日本の大学におけるスペイン語教育の制度的条件と環境(7) —スペイン語教育の意義再考」 『スペイン語新文法(基礎編)』第2章 『語』 2b 第7節 『形容詞』 |
|
| 第95回 | 2016年2月13日 | 第7回 関西スペイン語教師の集い | |
| 第96回 | 2016年3月5日 | 「第7回関西スペイン語教師の集い」で扱ったテーマのふりかえり 「大学における必修科目としての第2外国語の存在意義」 『スペイン語新文法(基礎編)』第2章 『語』 2b 語類・語種 第9節 『冠詞』 |
|
| 第97回 | 2016年4月9日 | 『スペイン語学習のめやす』―紹介およびその適用可能性について― | |
| 第98回 | 2016年5月7日 | GIDE(2015)『スペイン語学習のめやす』を利用して所要時間20分の教案を作る -「言語運用」を重視しつつ文法項目を教える「20分教材」案 『スペイン語新文法基礎』 第2章 「語」 2b 語類・語種 第10節 「人称代名詞」 |
|
| 第99回 | 2016年6月4日 | -『外国語学習のめやす』の特徴―目標分解表、3x3+3、コミュニケーション能力指標―の具体例と授業実践報告 『スペイン語新文法基礎』第2部 「語」 2b 語類・語種第11章 「指示詞と所有詞」 |
|
| 第100回 | 2016年7月2日 | -『外国語学習のめやす』を利用して所要時間20分の教案を作る -テーマ9:体調と気分 (『学習のめやす』 pp. 56-57, pp. 121-122) 『スペイン語新文法基礎』第2部 「語」 2b 語類・語種第12章 「量化詞と数詞」 |
|


