
モルビアン県の県庁所在地であるヴァンヌです。ヴァンヌの名は、紀元前5世紀頃、この地にやってきたケルト人の一派ウェネト人の名前に由来するそうです。9世紀、フランス国王ルイ敬虔王よりブルターニュ公国を封ぜられたブルトン人土豪ノミノエが、ブルターニュ公国の首都として定めたのがここヴァンヌでした。10世紀に、首都はナント(現在ではロワール地方)に移されましたが、現在でもヴァンヌはモルビアン湾へとつながる港を持ち、人口約4,6000人を要する商業都市として、中世以来の繁栄を続けています。
旧市街東側には、13−17世紀に築かれた堅固な城壁が一部残っています。かつては城壁だけでなく城も擁したヴァンヌですが、現在では城壁に作られた市門が2つと塔が2本残るのみです。城壁の外側の堀沿いには、17世紀のものといわれる屋根つき洗濯場が残っています。水辺に沿って女性たちが横並びになり、たくさんの洗濯物を洗ったんだろうなぁ、と想像したのですが、あまりに水が汚かったので辟易してしまいました。まさか、17世紀当時にはもっと水はきれいだったはずですよねぇ…。でも、昔は現在ほど排水施設は発達していなかったはず…。そう考えると、もしかしたらもっと汚い水で洗濯をしていたのかもしれませんね…。
旧市街の中心には、13世紀初頭に建てられた聖ピエール大聖堂があり、この辺りには木骨組造りの家々が立ち並ぶ地域になっています。近くには考古学博物館もありますが、私がヴァンヌを訪れたときは閉まっていました。考古学博物館があるシャトー・ガイヤールはシャトーってぐらいだからお城なのかな??と期待したのですが、お城ではなく、中世当時ブルターニュ議会が置かれていた議事堂なのだそうです。考古学博物館のお向かいにあるレストランの壁の隅には、“ヴァンヌとその妻”と名付けられた陽気な彫刻がくっついています。中世時代からこの町を見続けてきたご夫婦だそうですが、いったい何のために作られた彫刻なのでしょうね?日本でいうところの鬼瓦のような役目のためなのでしょうか??それにしても、こう陽気な表情だと悪魔だって逃げちゃくれないだろうな、と思ったのでした…。
さてさて、忘れちゃいけない、ヴァンヌにまつわるヘンリー7世です。1471年、ブルターニュに流れ着いたヘンリーとジャスパー叔父さんは、ナントにいたブルターニュ大公フランシス2世に謁見した後、ヴァンヌにあったヴァンヌ城(Chateau de l'Hermine)に滞在することになります。スッシーニョ城へ移るまでの約一年間、二人はヴァンヌで過ごしました。その後、それぞれがLargoet城やジョスラン城で月日を過ごした後、二人がヴァンヌに戻ってきたのは、悪夢のようなサン・マロ事件でヘンリーがイングランドの手から逃れた1476年のことです。1483年秋には、南イングランドを主体としたイングランド貴族やジェントリ階級の者たちが多数ブルターニュに亡命し、ヘンリーとジャスパーに加わります。イングランド王リチャード3世に反旗を翻し蜂起したものの、返り討ちにあって蹴散らされブルターニュにやってきた彼らと共に、ヘンリーはイングランド王位に向かって動き出すことになるのです。ヴァンヌにいたヘンリーの下に集まった亡命者たちは数百人にのぼったといわれ、彼らの多くはヘンリーがイングランド国王になった後も、彼の臣下として宮廷で重用されることになりました。
長期間の亡命生活と、もともとイングランド貴族の中に親族が少なかったヘンリー・テューダーなる青年は、ヘンリー自身がイングランド国内のことに無知であっただけでなく、イングランド貴族たちにとっても未知の人物でした。そんな彼らがイングランドを離れた異国の地で共同体を営み、共に亡命生活を送ることによって、お互いの中に奇妙な連帯感を持つようになります。1483年から1485年の2年間の間に築かれた信頼関係は、その後のヘンリー7世の宮廷を支える上で大きな役割を果たしたそうです。彼らがヘンリーを玉座に就けるためにあれこれ策略を練る場となったヴァンヌ城が残っていないのは、なんとも残念なことですね。きっと15世紀後半のヴァンヌでは、野心に燃えるイングランドの男たちが数多く生活していたのでしょうね。あ〜タイムマシンが欲しい〜!!
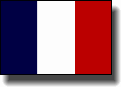 |
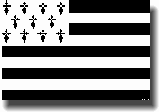 |
|
|
|