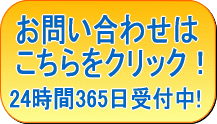|
|
印紙税は、契約書等の文書にかけられる税金です。
どういう文書に印紙税がかかるかは、印紙税法に規定されています。印紙税がかかる文書を課税文書といいます。
課税文書はその名称や形式を問いません。よく言われるのは覚書でも課税要件を満たしていればかかります。
なぜ文書を作成しただけで税金がかかるのかについては、文書の作成が税金を納めることのできる経済力を示しているから、といわれています。
つまり、そういう文書を作るのはお金があるからですよね、というのが課税の根拠なのです。
印紙がないからといって、契約書の効力には何の影響もないので、納税者にとっては理解しにくい税金のひとつだと思うのですが、課税文書には貼付するようにしてください。
>>このページのトップへ
|
|
|
金銭又は有価証券の受取書(要は領収書です)は三万円以上であれば印紙税の課税文書になりますが、「営業に関しない受取書」は課税対象から除かれています。
「営業に関しない」とは事業ではないものですから、個人事業主でない個人が領収書を発行したような場合や、公益法人が発行する領収書なども当てはまります(NPO法人の作成する領収書は課税文書です)。
なお、クレジットカードの使用による領収書には印紙は必要ありません。実務的によく質問を受けますのでしっかり押さえておいてください。
>>このページのトップへ
|
|
|
|
印紙の貼付の有無によって契約書が無効になることはありません。そうなると、こういう風に考える人がいるでしょう。
とりあえず契約の時は印紙を貼らないでおこう。万が一税務署が来たときには、事前に貼っておけばいい。そうすれば経費の削減につながる。
考え方の是非はともかく、対税務署ということを考えるとその方法は必ずしも有効ではありません。
印紙の図柄は定期的に変更されており、税務職員は図柄の一覧表を所持しているといわれています。
ですので、契約時と貼付した印紙の時期的なズレを指摘される可能性があるわけです。
課税文書には印紙を貼付しなければなりません。契約時に貼付しておくようにしましょう。
>>このページのトップへ
|
|
|
印紙税を貼付すべき課税文書に貼っていなかった場合、過怠税という罰金が課されます。
過怠税は本来はるべき税額の3倍です。1万円の印紙がない場合、3万円分収めないといけません。
そして、過怠税は税法上経費にはなりません。ですので、非常に重い罰金となっています。
このように罰金が重いのは、印紙税が自主的に納付する形式を取っているためと思われます。納税者が定期的に申告するわけではないので、罰金を重くして納付の定着を図ろうということなのでしょう。
ちなみに、印紙税の納付漏れは納税者の故意・過失を問いません。うっかりしていたという理由は通りませんので、十分ご注意ください。
>>このページのトップへ
|
|
|
印紙税は課税文書にかかるのですが、課税文書というのは紙で作成された文書をいいます。
ですので、例えばメールのやりとりのみで契約したような場合は印紙税はかかりません。ただし、メールを印刷目的で作成していれば課税文書と認定される可能性もあります。
契約書などの場合は通常は複数作られますが、一般的には複数の文書は同じものが作られますので、そのすべてがそれぞれ課税対象となります。
単に原本をコピーしただけのものは課税文書ではありませんが、そこに原本と相違ない旨の記載があれば、課税文書となります。
もう一つ、 外国で作成された文書には印紙税はかかりません。節税のためにわざわざ外国で契約書を作られる方はおられないかもしれませんが、海外取引も増えている時代ですので、該当する方は十分注意してください。
>>このページのトップへ
|
|
|
印紙税の節税方法には下記のようなものがあります。
1、消費税は除く
印紙税額は課税文書の記載金額で判断します。消費税の課税事業者の方は 消費税を区分して文書を作成すると節税になります。そうすることにより、消費税を含まない金額で税額を判定することになるからです。
例えば、請負契約の場合で
本体価格980万、消費税49万、合計1,029万と記載すれば印紙税額は10,000円ですが、両者を区分せず合計のみの記載の場合印紙税額は20,000円になってしまいます。
ただし、この方法は
- 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
- 第2号文書(請負に関する契約書)
- 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
の3つの文書にしか該当しない規定ですので、例えば手形の発行等の場合は当てはまりません。
2、金額を分割する
印紙税は 課税文書ごとにかかりますから、金額が大きな契約の場合は契約を複数にしてしまえば印紙税の合計額が減少することがあります。
例えば1億500万円の金銭消費貸借の場合に総額で契約すれば印紙税額は10万円ですが、9億9百万と6百万に契約を分割しておけば印紙税額は6万と1万の計7万となります。
3、金額変更時は差額のみ記載
当初の契約金額が増額に変更されたような場合は、変更した差額の金額のみ記載するような契約をすればその 差額分だけの印紙税の負担で済みます。
変更前との差額が分からないような契約の仕方をすると変更後の金額総額で税額を判定しなければなりません。
当初金額より減少した場合にも変更前との差額のみを記載すれば、金額の記載のない文書として、低い税額が適用されます。
4、契約内容の区分
例えば部品の販売と備え付け工事の仕事でしたら、本来は 工事部分のみが課税文書となります。
しかし、そこで契約内容を工事一式としてしまえば販売部分も含めた金額で税額が判定されてしまいます。
ですので、部品部分と工事部分の金額を別記載しておくと結果的に印紙税の節約になります。
5、メールのみのやりとり、そもそも作成しない
別項で述べたとおり、メールのやりとりのみでしたら課税文書にはなりません。
口頭での契約であっても契約自体は有効に成立しますからそれも節税方法といえるかもしれません。実行される方は少ないかもしれませんが。
>>このページのトップへ
|
|
|
実際の必要税額より多い印紙を貼付してしまったり、印紙を貼付した課税文書が破損等により使えなくなった場合は、税務署に申請すれば印紙税額が還付されます。
また将来的に使用する見込のない未使用の印紙をお持ちの場合は郵便局で手数料を5円払って他の印紙と交換することも可能です。
今後使う可能性のない高額な印紙をよく使うであろう200円の印紙と換えてもらうことができるのです。
いずれも便利な制度だと思いますので、そのような制度があるということを頭の片隅にでも留めておかれるといいと思います。
>>このページのトップへ
|