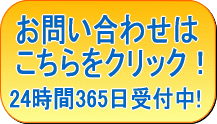|
|
所得税法では源泉徴収の対象となる支払いが定められており、その定められた支払に該当するときは、その支払をする者に源泉徴収義務が発生し、支払の際に源泉徴収しなければなりません。
身近なものとしては、給料や利子の支払があります。
サラリーマンの方でしたら、毎月の給料から源泉所得税が控除されていると思います。
それは、会社が給料を支払う際に源泉徴収義務を負っているからなのです。
>>このページのトップへ
|
|
|
| 源泉徴収した金額は、原則は徴収の翌月10日までに税務署に納めなくてはなりません。
しかし、小規模事業者(毎月の給与の支給人員が10人未満)は一定の届出をすることにより、年2回の納付で済ませることができます。
この届出をすることにより、1月から6月分までを7月10日に、7月から12月分までを1月10日(選択すれば20日)までに納付することができます。
資金繰りも楽になり、事務の手間も省けますので、該当される方は是非とも届出されることをおすすめします。
>>このページのトップへ
|
|
|
|
アルバイトだから、源泉徴収されないということはありません。そういう法律があると、アルバイトを装って源泉徴収をやめる方が出てこないとも限らないからです。
あくまで実際の支払に応じて源泉徴収されます。
>>このページのトップへ
|
|
|
給料を支払う際には源泉徴収する必要がありますが、源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
表の使い方としては、月給・日給・賞与のそれぞれについて「月額表」「日額表」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめて源泉徴収税額を計算します。
要は給与の支払形態と金額に応じて、表から算出することになります。
なお2ヶ月を超えて継続勤務している場合は、たとえ日給計算でも月額表を使って源泉徴収がされますので、ご注意ください。
>>このページのトップへ
|
|
|
| 給料の支払いは源泉徴収の対象になりますが、給料の支払いとはお金だけでなく、物でもらったり、特別の便宜を受けたりすることも含みます。
この経済的利益のことを現物給与といいます。
現物給与を供与することは給与の支払いと同じように取り扱われ、源泉徴収をする必要があります。
税務調査の中には源泉徴収のみを対象とするものがあり、そこでは細かい現物給与までチェックされます。
実務的にも現物給与の源泉徴収漏れは多いので、従業員への福利厚生等については、規定をよく確認してください。
>>このページのトップへ
|
|
|
現物給与はすべてが源泉徴収の対象になるわけではありません。
種類や金額に応じて、非課税とされるものもあります。
分かりやすい例として、通勤手当は月額10万円まで課税されませんが、このように課税対象から除かれているものがあるのです。
ということは、それらの規定を上手く利用すれば従業員の福利厚生を充実させながら、節税にもつながることになります。
>>このページのトップへ
|
|
|
非課税とされる現物給与のうち代表的なものは下記のとおりです。
参考にしてみてください。
1 法令の規定により課税しないこととされている現物給与
- ●通勤用定期乗車券(所法9(1)五、所令20の2)
- 1か月当たり100,000円までの通勤用定期乗車券
- ●低利融資の利益(措法29)
- 給与所得者(役員を除く)に対する住宅用家屋
又はその敷地の購入資金の低利融資等による利益などで一定の要件を満たすもの
- ●ストック・オプションの行使による利益(措法29の2)
- 一定の要件を満たすストック・オプションを行使して株式を取得した場合の利益
2 取扱通達により課税しないこととされている現物給与
- ●永年勤続者の表彰記念品(基通36―21)
- おおむね10年以上の勤続者に対するもので、かつ、2回以上表彰を受ける者についてはおおむね5年以上の間隔をおいて行われるもので、社会通念上相当(金銭支給はすべて課税)な記念品
- ●創業記念品等(基通36―22)
- 創業記念品等でその処分見込価額が10,000円以下の記念品等
- ●商品、製品等の値引販売(基通36―23)
- 取得価額以上で、かつ、通常の販売価額のおおむね70%以上の価額で値引販売する商品等
- ●残業宿日直者の食事(基通36―24)
- 通常の勤務時間外における残業、宿日直者に対して支給する食事
- ●金銭の無利息貸付け等(基通36―28)
- (1) 災害等による臨時多額の生活資金の貸付けを受けたことによる利息相当額の経済的利益
(2) 使用者における借入金の平均調達金利など合理的な借付利率により利息を徴している場合に生じる経済的利益
(3) (1)及び(2)以外の貸付けによる経済的利益で年間5,000円以下のもの
- ●レクリエーション費用の負担(基通36―30)
- 社会通念上一般に行われているレクリエーションの費用(任意の不参加者に金銭の支給がある場合や役員だけを対象とする場合を除く)
- ●生命保険料等の負担(基通36―31、32)
- 使用者が負担した役員又は使用人を被保険者とする生命保険等の保険料で一定の要件に該当するもの、保険料等の負担でその月中の金額が300円以下のもの
- ●食事の支給(基通36―38の2)
- 給与所得者がその食事の価額の2分の1以上を負担し、かつ、使用者の負担額が月額3,500円以下のもの
- ●深夜勤務者の夜食代(昭59直法6―5)
- 深夜勤務者の夜食代(金銭)で勤務1回につき300円以下のもの
- ●貸与住宅(社宅)(基通36―41ほか)
- 使用者が役員又は使用人に貸与した住宅等の経済的利益(家賃相当額)で一定の要件に該当するもの
- ●宿日直料(基通28―1)
- 勤務1回につき4,000円(食事が支給される場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までのもの
- ●祝金品、見舞金等(基通28―5、9―23)
- 祝金品、見舞金等で社会通念上相当なもの
>>このページのトップへ
|
|
|
| 個人に払う下記のような報酬も源泉徴収の対象となります。
法人に支払う手数料や報酬で源泉徴収が必要なものはあまりないので、特殊な支払い以外が気にされなくてもよいと思います。
個人に対する下記のような料金の支払いの際は源泉徴収をしているかどうか、注意しておいてください。
- 原稿料、講演料、デザイン料
- 弁護士、公認会計士や税理士への報酬
- 外交員、集金人への報酬
- ホステス等の業務への報酬
>>このページのトップへ
|
|
|
| 報酬・料金を支払う際には、交通費等の実費部分も依頼者が支払うことがありますが、この実費負担部分も基本的には源泉徴収の対象になります。
例えば、報酬10,000円、交通費1,000円の計11,000円を支払う場合、
源泉徴収額は11,000円×10%=1,100円となります。
このような場合であっても、実費を直接業者に払っている場合は源泉徴収の対象にはなりません。
例えばタクシー業者に直接支払いをしたようなときは源泉徴収をする必要はありません。
>>このページのトップへ
|